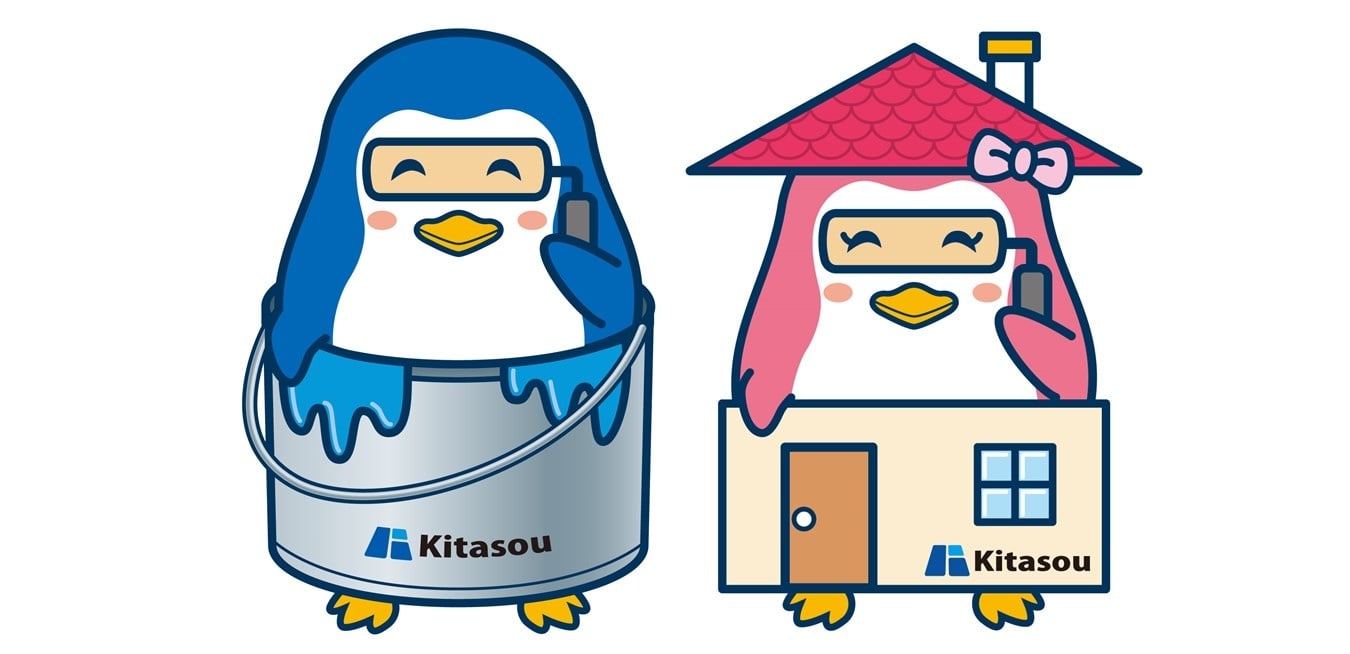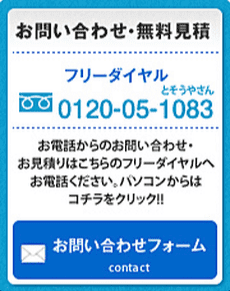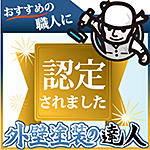色選びのマメ知識
どれだけ良い工事しても、どれだけきれいに塗っても、どれだけ長持ちしても、色選びに失敗したら台無しですよね。
10年に一度の外壁塗装の色選びを失敗させないために、ここでは「外壁塗装の色選び」のコツを紹介します。
外壁の色を決める手順
Step1.色を変えるか変えないか
<色を変えない場合>
なるべく北側の色あせをしていない壁面を、軽く絞った雑巾などで拭いて汚れを落とすと同時に、壁面をぬらします。
濡れ色になり、少し濃い目色になります。
この色が、色あせ前の色に近いものです。
見本帳のカラーサンプルを押し当てて比較し、最も近い色を探します。
→ステップ3へ
<色を変える場合>
一色仕上げ、ツートンカラー仕上げのどちらにするかを決めます。
Step2.色の系統を決める
外壁の色サンプルはそれこそ無数にあります。
サンプルシートとにらめっこしていてもなかなか決まるものではありません。
そこで、いきなりサンプルの中から色を選ぶのではなく、まずは色の系統を決めることをお勧めします。
グレー系、ベージュ系、ピンク系、イエロー系など、色の系統を決めてから具体的な色選びをはじめると、見るべきサンプルも限られ、選びやすくなります。
その際屋根、玄関ドア、サッシ等の色のバランスや近隣住宅との兼ね合いを考慮します。
カラーシミュレーションを活用すると良いでしょう。
<カラーシミュレーションの注意点>
カラーシミュレーションは色の系統を決める際には非常に有効です。
しかし、画像はモニター、印刷機のメーカー、機種等によって色合いが異なってきます。
最終決定に利用せず、全体イメージの参考にするのが良いでしょう
Step3.カラーサンプルから決める

色の系統が決まったら、カラーサンプルの中から近い色を探します。
サンプルは小さくて分かりにくいので、近い色をA4サイズの見本板で2~3枚ご用意させていただきます。
A4サイズの見本板が届いたら、その中から一色に絞ります。
外壁塗装の色選びのポイント
1.低彩度の色を選ぶ
住宅街では、周囲の環境を乱さない配慮が求められます。
彩度が高いと周囲の環境になじまず騒色となります。
高級感、落ち着き感もなくなります。
また、鮮やかな色は紫外線に弱いものが多いため色あせしやすい特徴があります。
そのような観点から、外壁塗装の色選びでは、彩度の低いカラー配色が中心となります。
2.配色は2~3色に留める
建物は部位によって使用されている材質も異なるものが多いです。
アクセントをつけるために、それぞれの部位を色分けすることも必要ですが、あまり多くの色を使いますと、全体の統一感、品格が損なわれます。
そのため、配色は2~3色に留める方が良いと思います。
どうしても多くなりそうなときは、同系色の濃淡でまとめるとスッキリします。
3.好みの色より似合う色

住宅は、そのデザインや建物の周囲との調和などで、似合う色と似合わない色があります。
塗り替えの色選びで失敗される方は、好みのみで色を選択する場合が多いのです。
あくまで似合う色を主眼に置いた色選びをおすすめします。
洋服の色や柄を選ぶ場合と同様で、好みの色と似合う色は違うことを念頭に置いてみてください。
色の見え方
1.面積の違いによる色の見え方

同じ色でも大きな面積と小さな面積とでは色の見え方が違います。
これを色の面積効果といいます。
明るい色はより明るく、鮮やかに見えます。
反対に暗い色はより暗く感じられます。
外壁塗装では淡彩色はワンランク濃い目の色、濃色はワンランク薄めの色を選ぶのがポイントです。
2.天候による色の見え方
色は光の照射量に影響されます。
曇りの日とよく晴れた日では光の照射量に差がありますので、色が違った感じに見えます。
よく晴れた日の、大気の汚れの少ない朝日の光でA4サイズの見本板を見るのが理想です。
3.艶消し塗料の色の見え方

艶消し塗料は艶有り塗料に比べ、いくらか白っぽい感じに仕上がります。
A4サイズの見本板で確認しましょう。
4.凹凸による色の見え方

外壁塗装は、スタッコ調の模様やサイディングの模様によって影ができ、その影響で色目が濃く感じることがあります。
フラットな面への塗装は薄めの色に仕上がります。
A4サイズの見本板で確認しましょう。
ツートンカラーの配色
ツートンカラーにしたい場合は、まずどこで区切るかを考えます。
上下に分けたり、出っ張っている部分だけに色を付けるなど様々な分け方があります。
ツートンカラーを成功させるポイントは、色量のバランスと色の組み合わせです。
色量のバランスは、2色を5:5にするのではなく、6:4か7:3程度にまとめるとバランスよく見えます。
また、上下に塗り分ける場合は、下を濃い目にすると落ち着き感が出ますが、あえて逆にするパターンも増えてきています。
色の組み合わせ方は、同系色でグラデーションにする方法、大きく違う色でメリハリをつける方法などがあります。
微妙に違う2色を組み合わせると、色を継ぎ足したように見えたり、ぼけた感じになりますので注意しましょう。












付帯部の色の決め方
軒天

軒天の色は基本的に明るい色で塗装することをお勧めします。
それは軒天は影になるので暗く見えるという点と、部屋内から外を見た際に明るく見えるからです。
白系、もしくは外壁の少し薄めの色を選ばれると良いでしょう。
雨樋
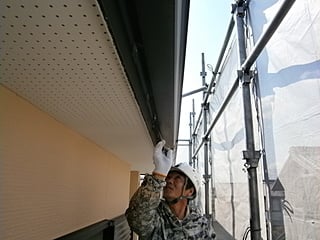
雨樋等の色を決める際に、一番無難かつお勧めなのはサッシ色に合わせることです。
黒サッシであれば黒色、白サッシであれば白色、ブロンズサッシであればこげ茶色で塗装するのがお勧めです。
次にお勧めなのは外壁色に合わせることです。
外壁色に塗ることで雨樋等の存在を目立たなくさせます。
その他付帯部
雨戸やシャッターBOXはサッシ色に合わせるのがお勧めです。
庇(ひさし)はサッシ色もしくは屋根色に合わせるのがお勧めです。
エアコンホースカバーは外壁色に塗って目立たなくする、もしくは雨樋と同じ扱いでサッシ色に塗装し、アクセントにするのがお勧めです。
色見本帳について
日本塗料工業会 色見本帳

この見本帳は建築物・設備機器・警官設備・インテリアカラーなど、一般に多く用いられる実用色を収録しています。
そのため、この中には外壁にふさわしくない色、色あせしやすい色も含まれております。
どうしても標準色に希望の色が無い場合は、担当者に相談の上、この見本帳から選びましょう。
塗料メーカー提案色

一般の住宅塗装において外壁の色を決める場合は、各塗料メーカーのカタログで提示されている標準色の中から選ぶことをお勧めします。
それは、外壁に適した色彩、色あせしにくい色、最新の住宅の配色の傾向等を考慮したメーカー推薦の提案色だからです。
外壁・屋根の色決めの参考にしてください。
最後に

ここに提案させていただいた色は無難な色ばかりです。
逆に全く違う色を塗装して、遊び心を出すのも面白いと思います。
カラーシミュレーション、住宅フィルムシート、A4サイズの見本板等で色選びの最大限のサポートをさせていただきます。
10年に一度の塗り替え工事、楽しく色決めしてください。